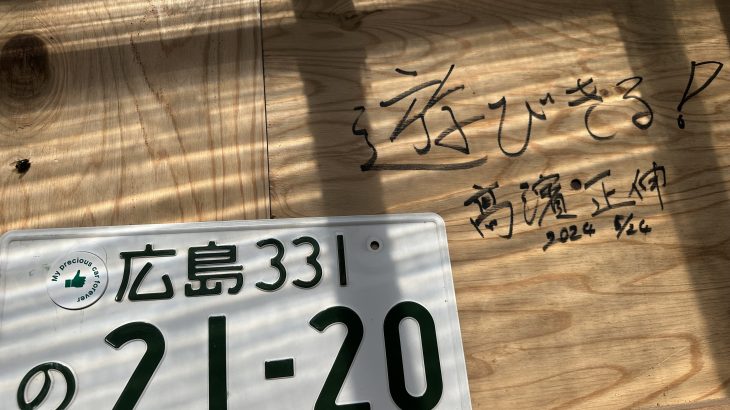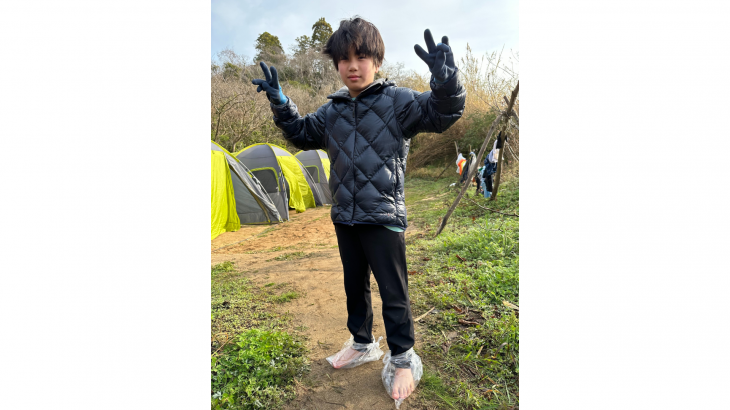4年近く続けてきたこのレポートも、そろそろ終わりだ。話の最後に、最初の話をしようと思う。私が広島に来て、最初にした仕事のことだ。
私の最初の仕事は、言葉で島を定義することだった。テントサイトの開拓だとか、備品の買いつけだとか、受け入れのしくみを作るだとか、ほかにもいろいろな仕事があったが、何よりも優先したのは「この島が何のためにあるのか」を言葉にすることだった。
実は、日本にはかなりたくさんの無人島がある。インターネットで検索すれば、無人島に行けるサービスは割と簡単に見つけることができるのだ。だから、ただ無人島であるということだけで、この先何年も人を惹きつけていくのには限界があると思った。数ある無人島のなかで、花まる子ども冒険島は何のための島であるべきなのか。それに答えを出すことで、島が生き残るための指針が見えてくる。
答えはすぐに出た。教育である。「子どもたちが、メシが食える大人になるための体験をする島」。その教育を目的とした島であると、言葉で定義する。そうすることで来島に独自性が生まれ、この先我々が何かに迷ったときには、この基準に立ち返ることができるようになる。具体的にどんな言葉にしたかは、ここでは触れない。ぜひ花まる子ども冒険島のHPで確かめていただきたい。すべての始まりになった言葉だ。
言葉の話でいくと、「冒険」という言葉についても私には特別な想いがあるので、伝えておきたい。冒険とは、「険を冒すこと」。つまり、「険」が存在する領域に踏み込んでいくことを意味する。では、「険」とは何か。まず思いつくのは「危険」ではないかと思う。しかし、私はこれを「リスク」であると考えている。危険とリスクの違いは、作家の村上龍がわかりやすく伝えているので、引用ではなく記憶からになるが、以下に紹介したい。
例えば、目の前に地雷原があるとして、そこにただ入ろうとするとき、地雷原は「危険」になる。しかし、その先に何か宝物があって、それを取りに行こうとするとき、地雷原は「リスク」になる。つまり、リスクとは、冒すべき価値のある危険を指す。リスクという言葉にはそうした日本語に翻訳できないニュアンスがふくまれているので、言い換えることができない。だから、リスク、とそのまま使う必要がある。
花まる子ども冒険島の「険」は、まぎれもなく「リスク」だ。ただの危険ではなく、冒すべき価値がある。人は時々、人生をそっくり変えてしまうような素晴らしい何かと出合うことがあるが、そうした出合いは必ずリスクのあるエリアで起こる。そのエリアは「外」と呼ばれる。外とは、ドアの外、すなわちアウト・ドアだ。安心や安全が保障されたドアの内側では、「何か」に出合うことはないだろう。身体的にも、精神的にも、我々は常にドアの外に赴く必要がある。花まる子ども冒険島が、100年先まで真にアウト・ドアであることを、心から願っている。
花まる学習会 橋本一馬

【無人島レポート-2022冬-】小屋づくり をはじめから読む
【無人島レポート-2022夏-】社員開拓団 をはじめから読む
【無人島レポート-2021初夏-】醤油メシ をはじめから読む
【無人島レポート-2021初夏-】ドラム缶風呂 をはじめから読む
花まる子ども冒険島
モノであふれた社会とはかけ離れた島、無人島。
今日を生き抜くために、頼りになるのは自分の心。
そこは、野外体験の究極の場となる。
強い『心』と自分の『目』を磨き、『自分の言葉』で語れる人に。
心と身体を強くする、花まる子ども冒険島が、いま始まる。
https://hanamarumujinto.wixsite.com/home
\最新情報を更新中!/
花まる子ども冒険島Instagram
https://www.instagram.com/hanamaru_mujinto/
花まる学習会 野外体験サイト
https://hanamaruyagai.jp/