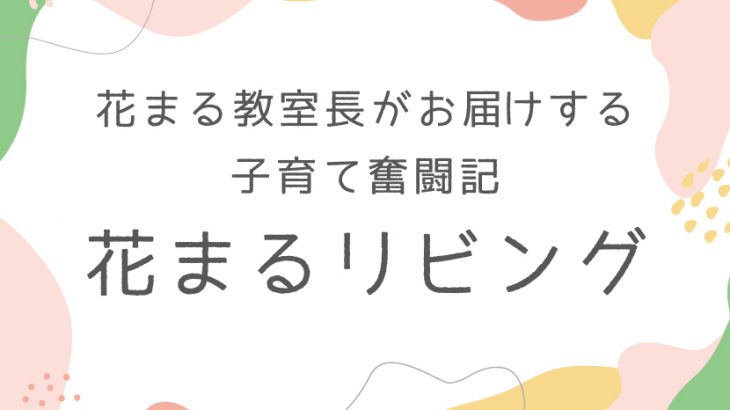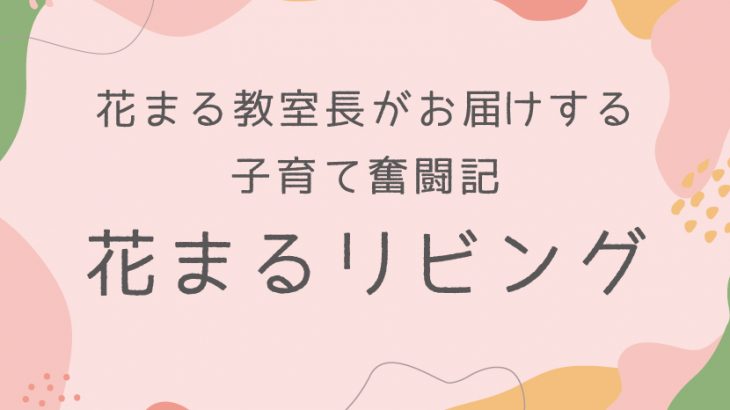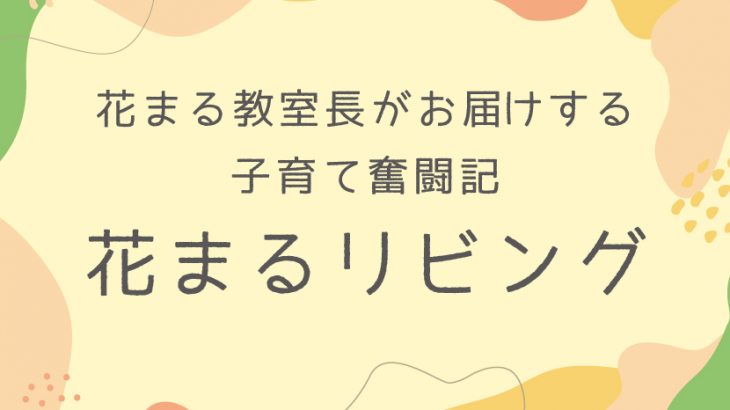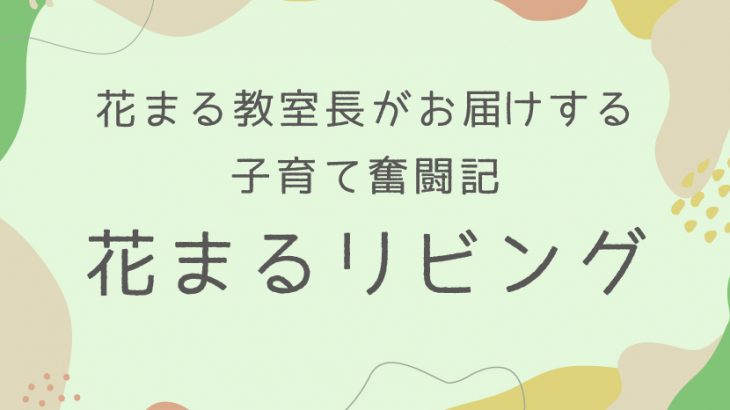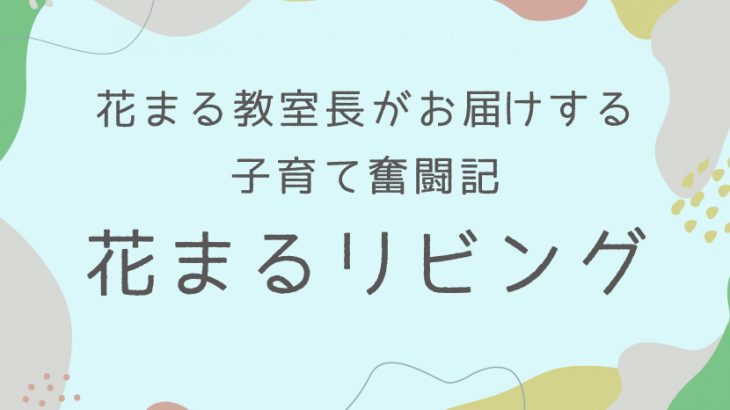長女が0歳のときから始めた絵本の読み聞かせ。
いまでは11歳の長女に読んであげることはなくなりましたが、8歳の長男にはときどき、3歳の次女には寝る前やせがまれたときに読み聞かせをしています。
「会話がメイン」の読み聞かせ
最近、長男が持ってきたのは『切り身の図鑑2 肉』(星の環会)。
牛肉や豚肉、鶏肉などの切り身についてのさまざまな情報が載った本で、「部位の名前と解説のところだけ読んで」とリクエストされました。
「ロース、ヒレ、バラ……」と読み上げるたびに、長男が言葉をはさんできます。
「100人が牛タンを食べたいときは、牛が100頭必要ってこと?」
(いや、牛の舌って想像以上に大きいから……)
「ささみの白いすじって取るの? 逆にそれだけ集めて、丸めたらおいしいかも!」
(お、おう……そうだね?)
なるほど~と思いました。自分でも快適なスピードで読めるとは思うのですが、あえて「読んで」と持ってきたのは、いま興味のあることに対して、大人と「あーだこーだ」会話がしたかったのでしょう。読み聞かせ=物語を聞かせることに重きを置きがちでしたが、こんな“会話メイン”の読み聞かせも楽しいものだなぁ、と新たな発見でした。
「絵本との出会いを演出する」読み聞かせ
一方、次女への読み聞かせは、なかなか手ごわいです。
兄への読み聞かせ中でも待ちきれず、「自分の本を読んで!」と割り込んできますし、お気に入りのセリフになると「ここは自分が読むからね!」と本を奪います。
しかも、同じ本を何度も何度も読みたがる。それ自体はまったく悪くないのですが、私としては正直飽きてしまって……。早く寝たくてちょっと文章を省略したら、「いまとばしたよね?」と鋭く詰め寄られます。姉や兄は、いま思うといわゆる「スタンダード」な読み聞かせが向いていたタイプ。次女はまた、まったくちがうタイプです。
そんな次女にここ最近ハマっているのが、「絵本との出会いを演出する」読み聞かせ。
花まる学習会の年中授業で、「風船」や「石」など“ものそのもので遊びきる”という時間があります。本誌でもコラムを連載しているRinの研修で「素材との出会いを丁寧に演出してあげると、子どもの自然発生的な気づきが生まれ続ける」という言葉を聞いて、「これ、絵本の読み聞かせにも応用できるかも」と思いつきました。
その日、次女が持ってきたのは、何度も読んだ『ぬまの100かいだてのいえ』(偕成社)。いつもならすぐ読みはじめるところを、表紙をじーっと見つめてから言いました。
「この『ぬ』のくるんとしたところ、おたまじゃくしのしっぽみたいだね」
「この緑色、普通より暗くて……なんだか“ぬまっぽい”ね」
私からはたった二か所についての声かけでしたが、それが呼び水になったのか、次女はページをめくるたびにどんどん自分の気づきを口にしていました。そんなことを考えるんだなぁ、と私にとっても発見の連続で、何度も読んだはずの絵本が新鮮に感じられるひとときでした。
子どもによって、読み聞かせのスタイルもまったく違うのがおもしろいところ。その違いも楽しみながら、これからも自由に、たくさん絵本とふれあっていけたらいいなと思っています。
花まる学習会 勝谷里美
🌸著者|勝谷 里美
 花まる学習会の教室長を担当しながら、花まる学習会や公立小学校向けの教材開発や、書籍出版に携わる。現在は、3児の母として子育てに奮闘中。著書に『東大脳ドリルこくご伝える力編』『東大脳ドリルかんじ初級』『東大脳ドリルさんすう初級』(学研プラス)ほか
花まる学習会の教室長を担当しながら、花まる学習会や公立小学校向けの教材開発や、書籍出版に携わる。現在は、3児の母として子育てに奮闘中。著書に『東大脳ドリルこくご伝える力編』『東大脳ドリルかんじ初級』『東大脳ドリルさんすう初級』(学研プラス)ほか