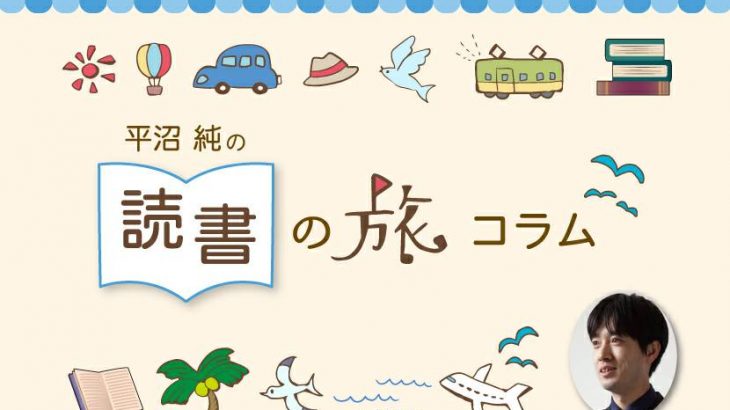子どもは、一度気に入った本が見つかれば何度でも読みたがります。
「あの本もう一回読んで!」と頼んできたり、同じ本を何度も図書館から借りてきてすり切れるまで読んでいたりということは、しばしばあります。
そんなとき、「もうそろそろ別の本を読みなさい!」という言葉を、つい言ってしまうのではないでしょうか。
たしかに親としては、子どもには可能な限りたくさんの本を読んで、いろいろなことに興味を持ってほしいと願うもの。
とはいえ、子どもが同じ本をくり返し読むことについては、まったく心配する必要はありません。
むしろ、「何度でも読みたいと思える、一生ものの本が見つかった」ことを喜べばいいのです。
子どもが何度も読んでいるということは、その本を最初に読んだときに感じた満足感を、くり返し味わいたがっている証拠です。
我を忘れて物語の世界に没入し、登場人物と一体化してさまざまな体験をし、そしてまた現実の世界に戻ってくるという、一種の快い旅のような体験。それがもたらす、「おもしろかった!」という純粋な充実感が、何よりも子どもの成長の糧になります。
■子どもは絵も読んでいる
また、これは特に絵本で言えることですが、実は子どもは絵本の文章だけでなく、「絵も読んでいる」のです。優れた絵本は、言葉だけではなく絵そのものも物語を語っていて、読むたびに新たな発見ができるものです。
『はじめてのおつかい』で有名な林明子さんの絵本は、探すと楽しい「遊び」が多く描かれていることで知られています。
たとえば、あきという女の子がキツネのぬいぐるみ「こん」と旅に出る、『こんとあき』という絵本。
表紙には駅の風景が描かれていますが、向かいのホームになぜかチャップリンやタンタン、『不思議の国のアリス』のアリスなどが立っています。
ほかにも、レイモンド・ブリッグズ『さむがりやのサンタ』のサンタクロースや、『ピーターラビット』シリーズに出てくるマグレガーさんなど意外なキャラクターも随所に登場して、子どもたちは楽しみながら探します。
また、以前、子どもたちに非常に人気があるジャック・ガントスの『あくたれラルフ』を読み聞かせていたときのこと。読み終わったあとに、ひとりの女の子が改めて表紙をじっと見て、「そういえば、赤いネコっていないよね」とつぶやきました。
これは、私もはっきりとは考えていなかったポイントでした。
この話は、セイラという女の子に飼われているネコのラルフが主人公。セイラが乗っているブランコの枝を切ってしまったり、お母さんが飼っている鳥を食べようと追いかけまわしたり……毎日あらゆる「あくたれ」をくり返します。
それは、あたかも内面からほとばしる衝動に突き動かされているかのよう。ラルフの「赤」は、この抑えんばかりの衝動、底抜けのエネルギーを表していて、この本に触れた子はそれを敏感に感じ取ったのです。
この本は、そのほかにも読むたびに絵からさまざまなものが読み取れます。ついに家族から見放されてサーカスに置き去りにされたラルフの絶望感、町のごみ捨て場で「ぼくさびしい」と泣くラルフの悲しみ、セイラと再会する場面の幸福感、そして最後のページの意外な「オチ」―――。
何十回、何百回とくり返し読む子もいるこの本ですが、それだけ、読むたびに話の筋だけでなく、絵からもさまざまな感情やメッセージ、物語が読み取れるのです。
どうか、子どもの「この本、もう一回読んで!」という言葉を、喜びとともに受け入れてもらえたらと思います。
スクールFC 平沼純
『はじめてのおつかい』筒井頼子 作/林明子 絵/
福音館書店
『こんとあき』林明子 作/福音館書店
『あくたれラルフ』ジャック・ガントス 作/ニコール・ルーベル 絵/いしいももこ 訳/童話館出版
 教育心理学を研究し、「自分の視点を持って考え、力強く生きていく力の育成」を目指して教育の世界へ。国語を専門とする学習塾で読書・作文指導などに携わったあと、花まるグループに入社。現在、小学生から中学生までの国語授業や公立一貫コース授業のほか、総合的な学習の時間である「合科授業」などを担当。多数の受験生を合格へ導くとともに、豊かな物語世界の楽しさ、奥深さを味わえる授業を展開し続けている。
教育心理学を研究し、「自分の視点を持って考え、力強く生きていく力の育成」を目指して教育の世界へ。国語を専門とする学習塾で読書・作文指導などに携わったあと、花まるグループに入社。現在、小学生から中学生までの国語授業や公立一貫コース授業のほか、総合的な学習の時間である「合科授業」などを担当。多数の受験生を合格へ導くとともに、豊かな物語世界の楽しさ、奥深さを味わえる授業を展開し続けている。
■著書紹介
『子どもを本好きにする10の秘訣』(実務教育出版)
著者:平沼純・高濱正伸
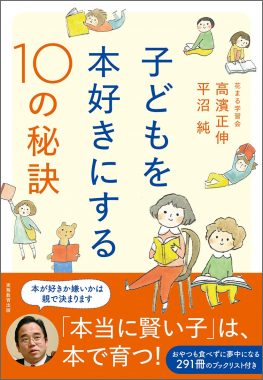
>>>書籍の詳細はこちら
📖2021年度 連続講座「旅する読書~大人のための読書講座~」開催中 !
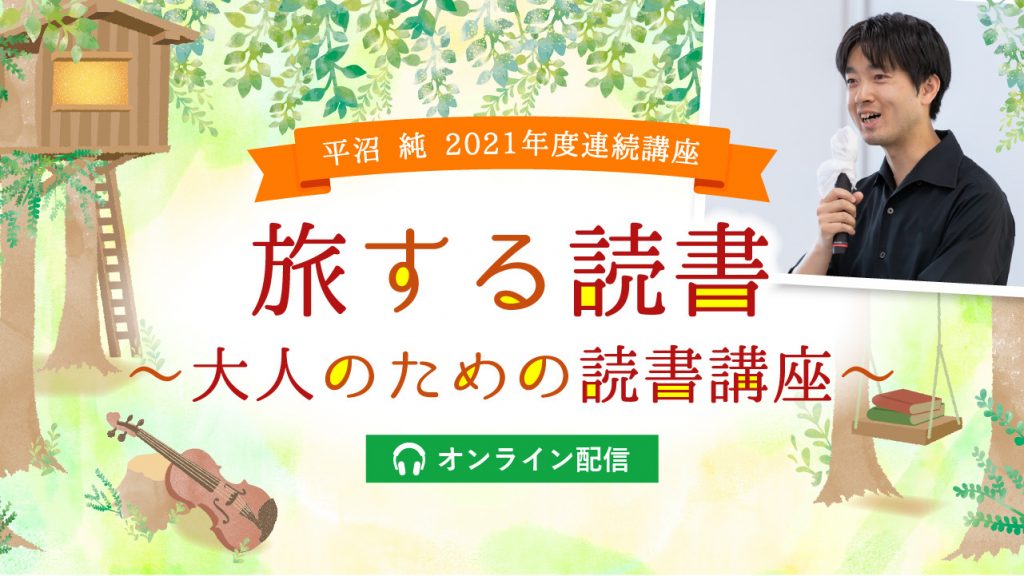
開催する度に大好評をいただいているスクールFC国語講師 平沼の連続読書講座。テーマに沿った本の紹介はもちろん、物語の舞台となった日本・世界の風景の上映、ゲストによる朗読劇や即興芝居、ミニ講座や対談などもお楽しみいただけます。奥深くて魅力的な物語の世界を味わえる時間を、ぜひご期待ください!
※回によって内容は異なります 。
>>> 開催日程・お申し込みなど詳細はこちら