「情報弱者」という言葉には、少し違和感を覚えます。本来、これはさまざまな事情で適切な情報や必要な情報を得られない弱い立場の人を指す言葉です。しかし、現代では「情報に疎いこと」がネガティブに捉えられることも少なくありません。
電車に乗れば、ほとんどの人がスマートフォンの画面に集中しています。「いかに早く有益な情報を手に入れるか」という強迫観念が、いつの間にか日常生活の大切な時間を奪っているようにも感じます。食事中もテーブルの片隅にスマートフォンが置かれ、電話やメール、LINEの通知音が鳴れば、会話の途中でも画面を見てしまうことに、あまり躊躇することもありません。あるファミリーレストランで見かけたご家族は、親はスマートフォン、子どもはタブレットを見ながら、片手間に食事をしているようでした。「将来、この子たちはちゃんとしたコミュニケーションを取れる大人になれるのだろうか」と思わず心配になりました。
受験の世界でも、情報戦が加速しています。特にはじめての受験では、右も左もわからないまま情報の海に迷い込むことが多いでしょう。受験は「一億総評論家」になれるテーマです。専門家でなくても、自分の経験をもとにさまざまな意見を語れる分野です。しかし、そこには真偽不明な情報や、閲覧数や「いいね」を狙ったフィクションも混在しています。一方で、非常に有意義な情報もあり、まさに玉石混交です。このなかから必要かつ正しい情報を選び出すことは、非常に難しい時代だと感じています。
受験において重要な一次情報は、学校が発信している公式な情報です。だからこそ「まずは学校に足を運んでください」とお伝えしています。また、わが子の学習状況に関する一次情報は、塾の担当者の言葉です。「面談や保護者会には必ずお越しください」とお願いしているのも、そのためです。 これらの一次情報を最初から疑ってしまうと、「もっと良い情報があるのではないか」と常に迷い続けることになります。もちろん、受け取った情報に疑問を感じることもあるでしょう。そんなときには、ぜひ遠慮せず相手に確認を取ってください。
学校や塾以外から得られる情報は、基本的に二次情報です。雑誌やメディア、SNSなどの情報は、どのように加工されて発信されているのかが不明なことが多いため、鵜呑みにせず、冷静に受け止めていただきたいと思っています。情報は「多ければ多いほど良い」というわけではありません。必要以上に取りに行かず、情報源をある程度固定して観察し続けることが大切です。世の中には、知らないほうがうまくいくこともあります。それでも気になることがあれば、塾経由で情報を入手することをお勧めします。所属校の担当者にご相談ください。
積極的に動いてほしいのは、学校見学です。早い段階から学校に足を運ぶのは、とても良いことです。まずは保護者の方だけで見学し、学校を絞り込んだうえで、子どもが参加できるイベントに連れて行くという方法もあります。 先日のVoicyでの保護者インタビューでも、「子どもを学校に連れていくと、直近に見学した学校を気に入ってしまい、そこが後悔ポイントでした」というお話がありました。たしかに、そうしたことはよくあります。
今年の受験生一人当たりの出願校数は、平均で8校程度だったようです。同一の学校に複数出願するケースもあるでしょうし、実際に受験したかどうかは別としても、それらの学校に絞り込むためには、2~3倍の学校見学をしているのではないかと推測されます。そう考えると、学校見学は少しずつでも始めたほうが良いでしょう。もちろん、すでにある程度志望校群が決まっている場合はそこまでではないかもしれません。しかし、入試には絶対はなく、子どもの成績にも波があります。受験するかどうか未定であっても、気になる学校には一度足を運んでおくことで、後々の選択肢が広がります。
情報は、量よりも質が大切です。親が情報に振りまわされてしまうと、最終的に困るのは子ども自身です。ぜひ、ご家庭の教育方針に照らし合わせて、慎重に情報を選択していただきたいと願っています。
スクールFC代表 松島伸浩
🌸著者|松島 伸浩
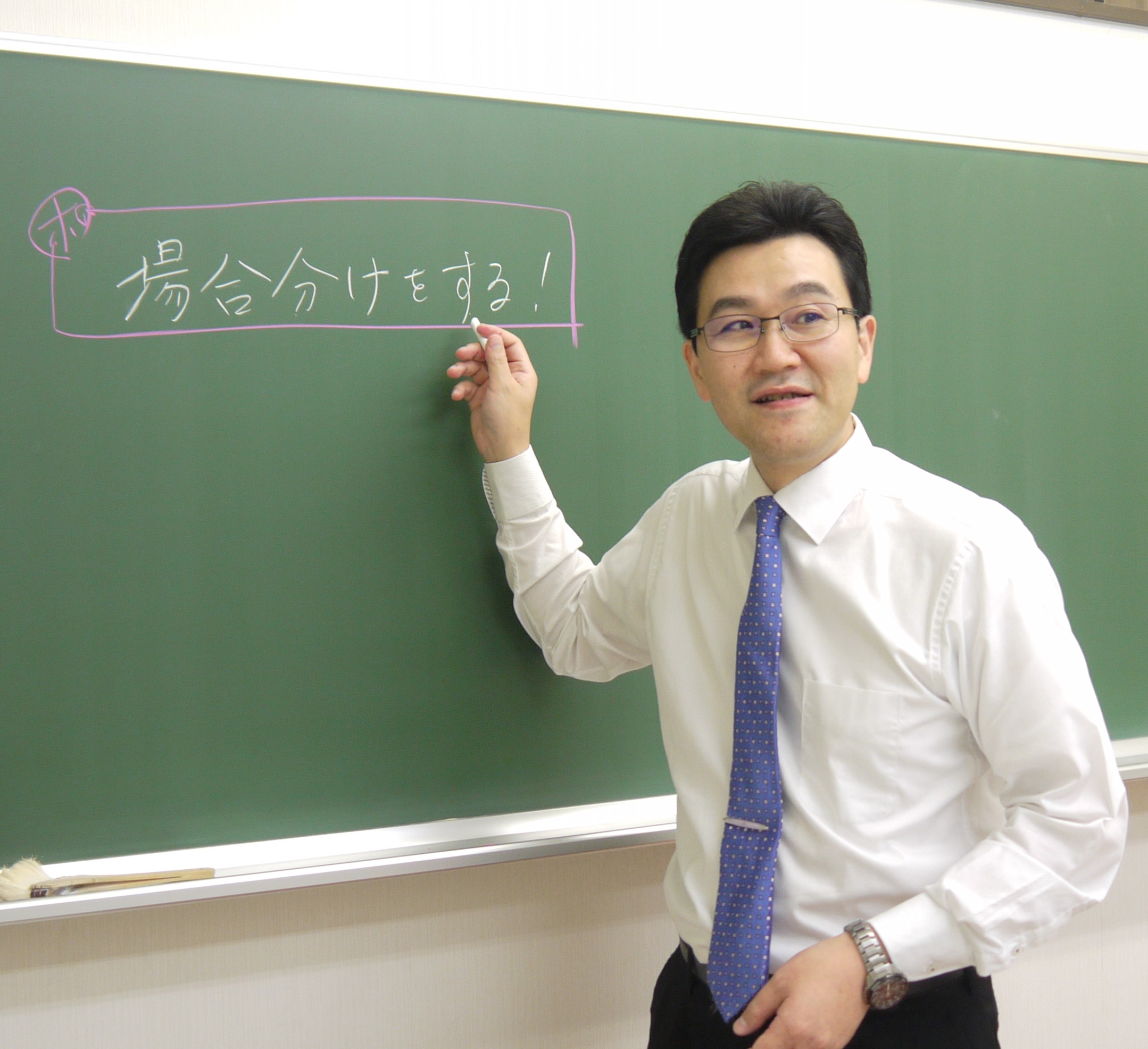 1963年生まれ、群馬県みどり市出身。現在、スクールFC代表兼花まるグループ常務取締役。教員一家に育つも、私教育の世界に飛び込み、大手進学塾で経営幹部として活躍。36歳で自塾を立ち上げ、個人、組織の両面から、「社会に出てから必要とされる『生きる力』を受験学習を通して鍛える方法はないか」を模索する。その後、花まる学習会創立時からの旧知であった高濱正伸と再会し、花まるグループに入社。教務部長、事業部長を経て現職。のべ10,000件以上の受験相談や教育相談の実績は、保護者からの絶大な支持を得ている。現在も花まる学習会やスクールFCの現場で活躍中である。
1963年生まれ、群馬県みどり市出身。現在、スクールFC代表兼花まるグループ常務取締役。教員一家に育つも、私教育の世界に飛び込み、大手進学塾で経営幹部として活躍。36歳で自塾を立ち上げ、個人、組織の両面から、「社会に出てから必要とされる『生きる力』を受験学習を通して鍛える方法はないか」を模索する。その後、花まる学習会創立時からの旧知であった高濱正伸と再会し、花まるグループに入社。教務部長、事業部長を経て現職。のべ10,000件以上の受験相談や教育相談の実績は、保護者からの絶大な支持を得ている。現在も花まる学習会やスクールFCの現場で活躍中である。





