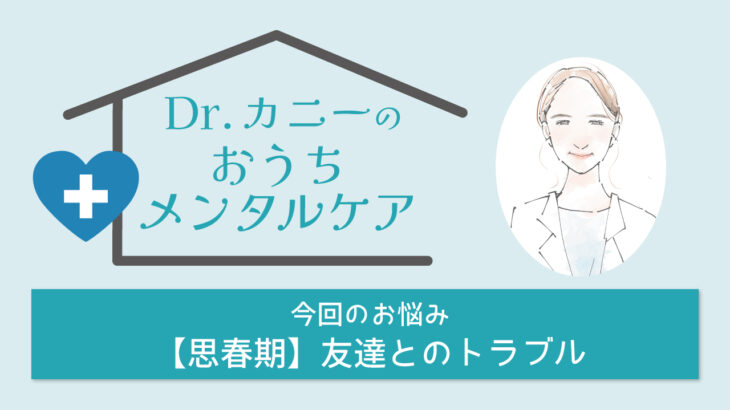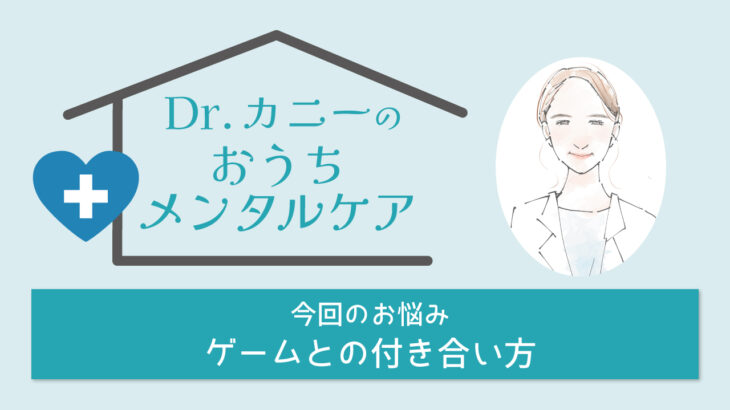【今月のお悩み 小5女子のママより 】
最近、学校で友達とトラブルがあったみたいで、宿題が手につかなくて、忘れ物も増えて……。 でも、私にはなにも話してくれないんです。
なんでも相談できる先輩のような存在もおらずただ一人で抱え込んでいるようです 親としてなにかできることはないでしょうか。
こんなとき、親としてとても心配になりますよね。「なにがあったの? 大丈夫?」と聞いても、 「うん、大丈夫」とだけ返されると、もどかしさや不安を感じるかたも多いのではないでしょうか。
今回は、思春期の子どもが親に話さなくなる理由や親としてできるかかわり方について、精神科医・感情教育の専門家としておうちでできる処方箋をお伝えします。
思春期は友達関係が難しくなる時期だけれど親に言わないのは成長の証
思春期は、心も人間関係も揺れやすい時期です。子どもは「自分とは何者か」を考えはじめ、親から心理的に距離をとろうとします。
孤独を埋めるように友達関係を重視しはじめますが、その友達関係でトラブルがあると、大きな悩みになります。しかしその気持ちを親に話すのは、簡単ではありません。
親に話さなくなるのは、子どもが「心配をかけたくない」「自分で解決したい」と思っている成長の証とも言えます。また、「親が重く受け止めすぎたらどうしよう」「話すことでつらくなるのが怖い」など、「感情との向き合い方」に関する不安がある場合もあります。
うつのサイン
一人で悩んでいると、「自分はダメだ」「自分は愛されていない」など悪いほうに考えがいきがちで、気持ちが沈んでいくことが多いです。心が疲れてくると、気力が出なくなったり、集中力が落ちたり、 忘れ物が増えたりすることもあります。これは「悲しみ」という感情が強かったり長引いたりしている サインかもしれません。悲しみが強く、2 週間以上気分が沈んでいる状態が続く場合は「うつ」の可能性も。眠れない、早朝に目が覚める、食欲がないといった症状があれば、早めに受診を検討しましょう。
普段の会話から「気持ち」を話しやすい環境を
では、子どもが話しやすくなるにはどうしたらいいのでしょうか?
大切なのは、定期的に一緒に料理をする、そばで洗濯物をたたむなど、自然に会話が生まれる空間をつくること、普段から気持ちについてやりとりできる環境をつくっておくことです。
感情に目を向けた声かけの例
・「元気がないように見えるけれど、大丈夫?」
・「悲しそうに見えるけれど、違ったらごめんね」
・「大丈夫」と返されたとしても、「気にしているよ」「いつでも味方だよ」と伝える
・無理に話させようとせず、「なにかあったらいつでも話してね」と声かけをしておく
・子どもが話してくれたときには、「話してくれてありがとう」と感謝を伝え、「それはつらかったね」と共感する
・すぐにアドバイスせず、「どうすれば力になれそう?」と子どもに尋ねてみる
・もし「聞いてくれるだけでいい」と言われたら、寄り添うだけで十分。逆に「先生に言ってほしい」などのSOSがあれば、子どもの気持ちを確認しながら行動する
最後に
高学年になると子どもの心の動きは見えづらくなりますが、「気にかけているよ」と伝えることが、子どもにとってなによりの支えになります。いま、お子さんは、「自分の気持ちと向き合う練習」をしているのかもしれません。日々の会話から「気持ち」について話しやすい環境をつくりつつ見守ってあげたいものです。
蟹江 絢子(かにえ あやこ)
 東京の大学病院にて児童精神科医として臨床に携わる傍ら、妊産婦やアスリート、神経発達症、精神疾患を対象とした認知行動療法の研究を行う。VRやアプリを活用した認知行動療法のプロダクト開発にも取り組み、精神医学・心理学の啓蒙活動を一般の方や教育業界向けに展開。二児の母としての経験も活かし、親としての目線で日々の生活や子育てに役立つ情報を発信中。
東京の大学病院にて児童精神科医として臨床に携わる傍ら、妊産婦やアスリート、神経発達症、精神疾患を対象とした認知行動療法の研究を行う。VRやアプリを活用した認知行動療法のプロダクト開発にも取り組み、精神医学・心理学の啓蒙活動を一般の方や教育業界向けに展開。二児の母としての経験も活かし、親としての目線で日々の生活や子育てに役立つ情報を発信中。
※花まるだより2025年7・8月号掲載